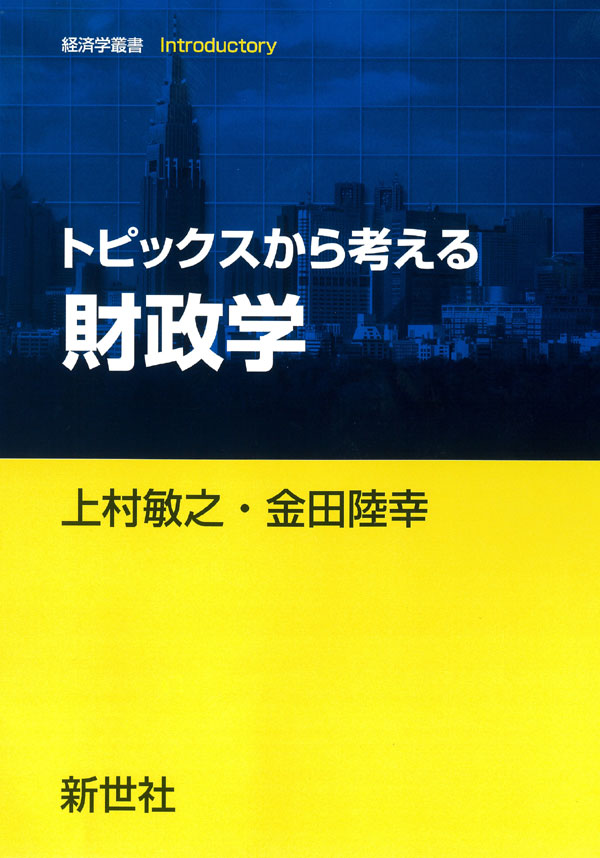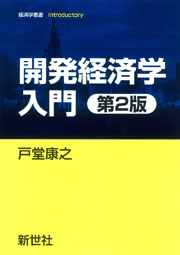第1章 政府の借金から考える財政学
1.1 政府の借金
1.1.1 実際:日本政府の借金残高の推移
1.1.2 制度:さまざまな種類の公債
1.1.3 理論:伝統的な公債負担論
1.2 歳入と歳出
1.2.1 実際:日本政府の歳入と歳出
1.2.2 制度:予算原則と予算編成の流れ
1.2.3 理論:財政政策の理論
第2章 身近な税金から考える財政学1
2.1 消費税
2.1.1 実際1:消費税の税収と使途
2.1.2 実際2:各国の付加価値税と軽減税率
2.1.3 制度1:消費税制の変遷
2.1.4 制度2:仕入税額控除
2.1.5 理論1:課税の経済効果
2.1.6 理論2:価格弾力性と超過負担
2.2 所得税
2.2.1 実際:所得税の税収
2.2.2 制度:所得税の仕組み
2.2.3 理論:所得税の経済効果
第3章 身近な税金から考える財政学2
3.1 法人税
3.1.1 実際:法人税の法定税率と実効税率
3.1.2 制度:法人税の仕組みと考え方
3.1.3 理論1:法人税の経済効果
3.1.4 理論2:経済学的な企業の実効税率
3.2 税とは何か
3.2.1 実際1:なぜ税が必要か
3.2.2 実際2:租税原則
3.2.3 実際3:垂直的公平と水平的公平
3.2.4 実際4:包括的所得税と支出税
3.2.5 制度:日本の税制
3.2.6 理論1:累進税と逆進税
3.2.7 理論2:労働所得税と消費税
第4章 身近な公共サービスから考える財政学
4.1 教育
4.1.1 実際:さまざまな公共サービスへの経費
4.1.2 制度:教育財政の仕組み
4.1.3 理論1:公共財としての教育
4.1.4 理論2:教育の外部性
4.1.5 理論3:望ましい公共サービスの水準
4.2 社会保障
4.2.1 実際:社会保障への支出と財源
4.2.2 制度:社会保障財政の仕組み
4.2.3 理論1:公的年金の必要性と財政方式
4.2.4 理論2:社会保険の必要性
第5章 財政再建から考える財政学
5.1 財政収支とプライマリーバランス
5.1.1 実際:財政収支とプライマリーバランスの推移
5.1.2 制度:財政再建計画・財政健全化目標
5.1.3 理論:財政の持続可能性
5.1.4 理論2:公債の等価定理と中立命題
5.2 行政改革
5.2.1 実際:行政改革の歴史
5.2.2 制度:行政評価・行政改革の制度
5.2.3 行政改革の理論
第6章 国と地方の関係から考える財政学
6.1 政府間関係
6.1.1 実際:国と地方の財政の関係
6.1.2 制度:地方交付税の仕組み
6.1.3 理論1:普通交付税による地域間所得再分配
6.1.4 理論2:地方自治体の人口規模
6.2 地方公共サービスと補助金
6.2.1 実際:目的別歳出と性質別歳出
6.2.2 制度:国庫支出金
6.2.3 理論1:受益のスピルオーバーと補助金の経済効果
6.2.4 理論2:地方分権化は望ましいか
第7章 財政の役割から考える財政学
7.1 財政の誕生の歴史
7.1.1 実際1:共同体から国家へ
7.1.2 実際2:前近代国家から近代国家へ
7.1.3 制度:コミュニティにもある財政に似た仕組み
7.1.4 理論1:社会契約説による国家の誕生と財政の誕生
7.1.5 理論2:近代国家から現代国家,戦争そして福祉国家へ
7.2 財政の3機能
7.2.1 実際:財政とは,財政学とは何か
7.2.2 制度:財政の範囲 ― SNAによる分類
7.2.3 理論1:家計,企業,政府の経済循環・市場の失敗
7.2.4 理論2:資源配分機能
7.2.5 理論3:所得再分配機能
7.2.6 理論4:経済安定化機能
7.2.7 理論5:国の財政と地方財政の役割
索引
1.1 政府の借金
1.1.1 実際:日本政府の借金残高の推移
1.1.2 制度:さまざまな種類の公債
1.1.3 理論:伝統的な公債負担論
1.2 歳入と歳出
1.2.1 実際:日本政府の歳入と歳出
1.2.2 制度:予算原則と予算編成の流れ
1.2.3 理論:財政政策の理論
第2章 身近な税金から考える財政学1
2.1 消費税
2.1.1 実際1:消費税の税収と使途
2.1.2 実際2:各国の付加価値税と軽減税率
2.1.3 制度1:消費税制の変遷
2.1.4 制度2:仕入税額控除
2.1.5 理論1:課税の経済効果
2.1.6 理論2:価格弾力性と超過負担
2.2 所得税
2.2.1 実際:所得税の税収
2.2.2 制度:所得税の仕組み
2.2.3 理論:所得税の経済効果
第3章 身近な税金から考える財政学2
3.1 法人税
3.1.1 実際:法人税の法定税率と実効税率
3.1.2 制度:法人税の仕組みと考え方
3.1.3 理論1:法人税の経済効果
3.1.4 理論2:経済学的な企業の実効税率
3.2 税とは何か
3.2.1 実際1:なぜ税が必要か
3.2.2 実際2:租税原則
3.2.3 実際3:垂直的公平と水平的公平
3.2.4 実際4:包括的所得税と支出税
3.2.5 制度:日本の税制
3.2.6 理論1:累進税と逆進税
3.2.7 理論2:労働所得税と消費税
第4章 身近な公共サービスから考える財政学
4.1 教育
4.1.1 実際:さまざまな公共サービスへの経費
4.1.2 制度:教育財政の仕組み
4.1.3 理論1:公共財としての教育
4.1.4 理論2:教育の外部性
4.1.5 理論3:望ましい公共サービスの水準
4.2 社会保障
4.2.1 実際:社会保障への支出と財源
4.2.2 制度:社会保障財政の仕組み
4.2.3 理論1:公的年金の必要性と財政方式
4.2.4 理論2:社会保険の必要性
第5章 財政再建から考える財政学
5.1 財政収支とプライマリーバランス
5.1.1 実際:財政収支とプライマリーバランスの推移
5.1.2 制度:財政再建計画・財政健全化目標
5.1.3 理論:財政の持続可能性
5.1.4 理論2:公債の等価定理と中立命題
5.2 行政改革
5.2.1 実際:行政改革の歴史
5.2.2 制度:行政評価・行政改革の制度
5.2.3 行政改革の理論
第6章 国と地方の関係から考える財政学
6.1 政府間関係
6.1.1 実際:国と地方の財政の関係
6.1.2 制度:地方交付税の仕組み
6.1.3 理論1:普通交付税による地域間所得再分配
6.1.4 理論2:地方自治体の人口規模
6.2 地方公共サービスと補助金
6.2.1 実際:目的別歳出と性質別歳出
6.2.2 制度:国庫支出金
6.2.3 理論1:受益のスピルオーバーと補助金の経済効果
6.2.4 理論2:地方分権化は望ましいか
第7章 財政の役割から考える財政学
7.1 財政の誕生の歴史
7.1.1 実際1:共同体から国家へ
7.1.2 実際2:前近代国家から近代国家へ
7.1.3 制度:コミュニティにもある財政に似た仕組み
7.1.4 理論1:社会契約説による国家の誕生と財政の誕生
7.1.5 理論2:近代国家から現代国家,戦争そして福祉国家へ
7.2 財政の3機能
7.2.1 実際:財政とは,財政学とは何か
7.2.2 制度:財政の範囲 ― SNAによる分類
7.2.3 理論1:家計,企業,政府の経済循環・市場の失敗
7.2.4 理論2:資源配分機能
7.2.5 理論3:所得再分配機能
7.2.6 理論4:経済安定化機能
7.2.7 理論5:国の財政と地方財政の役割
索引